シリーズ知恵ブクロウ&生きものハンドブック
Fly Me to the Moon ―月を目指した物語
2012/10/23
《中秋》だけではない、もう一つの「名月」を見上げながら、月を目指してきた人類の想像力とその結実に思いを馳せてみる。
もう一つの「名月」
旧暦八月十五日の中秋節こそ、誰もが知る"十五夜の月見"だが、嘗ての日本には、もう一つ独特の"月見"があったらしい。旧暦九月十三夜は、「後(のち)の月」と呼ばれる。晩秋を迎え豊穣を祝う収穫祭の赴であろう、豆名月や栗名月と呼ばれ、食べ頃の秋の実りを供えたのだそうだ。いずれかの月見しかしない「片月見」は縁起が悪いと、二つの月を愛でるのが江戸の遊興の流儀であったようだが、満ちる前、幾分の翳りを宿した月を佳しとするのも、日本ならではの感性であるかも知れない。
今年の中秋は天候に恵まれず"雨月"になった場所も多かったことだ。改めて、秋の夜に冴える月を見上げてみてはどうだろう。
「月世界」への想像力
 かぐや姫や嫦娥のように、月に昇る物語は、空に浮かぶ別世界を人が古来想像して来た一つの証左なのかも知れないが、月面に建設された基地や都市が登場する現代の様々なSF作品に先駆けて、近代科学の発達とともにかき立てられた宇宙への旅想の金字塔的作品を紹介しよう。
かぐや姫や嫦娥のように、月に昇る物語は、空に浮かぶ別世界を人が古来想像して来た一つの証左なのかも知れないが、月面に建設された基地や都市が登場する現代の様々なSF作品に先駆けて、近代科学の発達とともにかき立てられた宇宙への旅想の金字塔的作品を紹介しよう。
コペルニクスが地動説を唱え、ガリレイが望遠鏡で"地上と同じように不完全な"月の風景を暴いた17世紀、人々は科学に根差した想像力を宇宙に広げ、幾つもの仮説や物語が書かれた。エドモン・ロスタンの戯曲によって勇名を残すシラノ・ド・ベルジュラック、学者にして詩人、無双の剣客であった容貌魁偉のこの才人は、『月の諸国諸帝国』の中で、まだ存在もしなかった後の気球やロケットに通じるような発想で異世界を旅する空想を描いた。物語は随所に荒唐無稽だが、黎明にある科学が導いた想像力は私達が今見る世界の風景にも確かに続いている。
真実の「月世界旅行」へ
 2世紀を下って、『海底二万里』等数多くの作品でSFの祖となったジュール・ヴェルヌの『月世界旅行』はずっと著名だろう。ジョルジュ・メリエスに手掛けられた同作も、また映画史に残る作品だ。186X年、フロリダから巨大な大砲によって発射された砲弾に搭乗して、3人の男が月を目指す。二次曲線の弾道、真空と無重量状態、月面の詳細な観察、そして―軌道制御の失敗による―地球への帰還、太平洋への着水。言うまでも無く様々な描写が非現実的な空想であるが、しかし同時に19世紀、産業革命を経て科学が世界を著述する時代、月への旅は単なる夢想ではなく来るべき未来の"予言"めいた趣さえ帯びている。フロリダから打ち上げられたアポロ8号が、3人のクルーを乗せて初の有人月周回飛行を達成し太平洋へと帰還するのが、ほぼ100年後のこと。想像力から現実までのその時間は、十分に長すぎた、と言えるだろうか。
2世紀を下って、『海底二万里』等数多くの作品でSFの祖となったジュール・ヴェルヌの『月世界旅行』はずっと著名だろう。ジョルジュ・メリエスに手掛けられた同作も、また映画史に残る作品だ。186X年、フロリダから巨大な大砲によって発射された砲弾に搭乗して、3人の男が月を目指す。二次曲線の弾道、真空と無重量状態、月面の詳細な観察、そして―軌道制御の失敗による―地球への帰還、太平洋への着水。言うまでも無く様々な描写が非現実的な空想であるが、しかし同時に19世紀、産業革命を経て科学が世界を著述する時代、月への旅は単なる夢想ではなく来るべき未来の"予言"めいた趣さえ帯びている。フロリダから打ち上げられたアポロ8号が、3人のクルーを乗せて初の有人月周回飛行を達成し太平洋へと帰還するのが、ほぼ100年後のこと。想像力から現実までのその時間は、十分に長すぎた、と言えるだろうか。
Fly Me to the Moon, with Reason and Imagination
 一流の知識人だったシラノは、社会風刺ばかりではなく当時の科学知識をも豊かな文筆に乗せた。ヴェルヌの小説は、少年ヴェルナー・フォン・ブラウンの心を虜にし、やがてアポロ計画を主導して本当の人間を月へと送らせた。世人が或いは思う程、科学とは"夢想の対極にあるもの"なのだろうか。そうではない。世界の仕組みを知り、新しい視界に興奮し、その先に見えるだろう世界を想像して、やがてその想像を追いかけて現実の風景に出会う。科学とは、人の夢の見方そのものだ。
一流の知識人だったシラノは、社会風刺ばかりではなく当時の科学知識をも豊かな文筆に乗せた。ヴェルヌの小説は、少年ヴェルナー・フォン・ブラウンの心を虜にし、やがてアポロ計画を主導して本当の人間を月へと送らせた。世人が或いは思う程、科学とは"夢想の対極にあるもの"なのだろうか。そうではない。世界の仕組みを知り、新しい視界に興奮し、その先に見えるだろう世界を想像して、やがてその想像を追いかけて現実の風景に出会う。科学とは、人の夢の見方そのものだ。
ぼくはこう思うのだよ。
月もこの世界も同じような世界であって、
そこではわれわれの世界の方が月の役をつとめているのだとね。
ーシラノ・ド・ジルジュラック(赤木昭三訳)
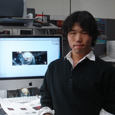
内藤 誠一郎(ないとう せいいちろう)
東京大学大学院にて電波天文学を学び、野辺山やチリの望遠鏡を用いて分子雲進化と星形成過程の研究を行う。
国立天文台では研究成果を利用する人材養成や地域科学コミュニケーションに携わり、2012年からは現職で広く学術領域と社会とのコミュニケーション促進に取り組む。修士(理学)。日本天文学会、天文教育普及研究会会員。東京都出身。
自然科学研究機構 国立天文台 広報普及員
(社)学術コミュニケーション支援機構 事務局長
天文学普及プロジェクト「天プラ」 プロジェクト・コーディネータ

