

12,14
2024年8月、循環型社会の形成を進めるための国家戦略「第五次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されました。これにより、資源消費の最小化と廃棄物の発生抑止、資源や製品価値の最大化を目指す「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への移行が加速されることになります。CSV経営サロンではこうした動向を鑑み2025年度のテーマを「資源循環」に定め、資源循環に取り組む有識者や先進企業と連携しながら全3回に渡ってその最新事情や取り組み方について考えていきます。
8月20日に三菱地所本社内で開催された第1回目では、環境省の小林豪氏(水・大気環境局 海洋環境課 プラスチック汚染国際交渉チーム長)、サラヤ株式会社の橋本典明氏(サニテーション事業本部 公衆衛生部 統括部長)と深澤恒正氏(商品開発本部 サステナブルデザイン開発センター ID課 専任課長)をゲストにお招きし、「国際プラスチック条約の動向と企業に求められること」というタイトルで講演とパネルディスカッションを実施しました。
講演に先立ち、CSV経営サロン座長の小林光氏(東京大学先端科学技術研究センター 研究顧問、教養学部客員教授)は、「プラスチック汚染問題は国際的な情勢を無視しては取り組めないものです。今まさしく国際規範ができつつある中、何をすればいいのか、実際に交渉をしたり、企業として動いたりしている方々から、成功譚ばかりではなく苦労話や困っていることを含めてざっくばらんに伺っていきたいと思います」と、この講演への期待を口にしました。
- 続きを読む
- プラスチック条約の合意を阻む壁
プラスチック条約の合意を阻む壁
 環境省の小林豪氏
環境省の小林豪氏
最初に登壇した環境省の小林豪氏は、プラスチック条約の策定を決めた国連環境総会決議の起草や、2023年のG7札幌環境大臣会合で2040年プラスチック汚染ゼロ目標を導くなど、日本においてプラスチック汚染問題に関する国際交渉をリードする人物のひとりです。2025年8月にスイス・ジュネーブで開催されたプラスチック条約交渉会合(INC5.2)でも分科会共同議長を務めており、INC5.2の概要や、プラスチック汚染問題を取り巻く世界の最新情勢について解説いただきました。
プラスチック条約の策定が決まったのは2022年3月の国連環境総会(UNEA)においてでした。当時から問題視されていたプラスチック汚染に対して法的拘束力のある国際文書(条約)を策定するために政府間交渉委員会(INC)が設置され、2024年末までに条文案の合意を目指すことが掲げられます。しかし蓋を開けてみると各国の主張がぶつかり合って交渉は難航。例えば、産油国側はプラスチック汚染を廃棄物管理の問題と捉え先進国の資金援助による解決を主張しますが、多くの国は生産から廃棄までライフサイクル全体で取り組むことを求め、特にEUや南米・アフリカ諸国などは生産そのものの規制が必要だと訴えています。
こうした行き違いは、現時点でプラスチック汚染が環境に及ぼす影響が国際的に定量化されていないことや、各国がどれだけのプラスチックを環境中に排出・流出しているかといったデータや科学的知見が不足していることが関係しています。また「共通だが差異ある責任(CBDR)」という考え方も影響しています。CBDRは、環境問題のような世界共通の課題はすべての人類が共通して取り組むべきものですが、歴史的に見ればその発端は先進国であることが多いため、先進国と途上国の責任には差異をつけるべきという考え方です。
小林豪氏は「温室効果ガスの排出ではCBDRの考え方は当てはまりますが、プラスチック問題については途上国からの流出が多く、必ずしも気候変動と同じような責任論を当てはめられるわけではない」と話しますが、現状ではこの考え方も合意を阻む壁となっています。こうした状況下で日本は各国のバランスを取るポジションに位置しているそうです。
「日本は『大量消費国・排出国が条約に参加し、世界全体で対策に取り組める条文を目指すべき』と一貫して主張しています。そのためには各国が果たすべき義務について柔軟性をある程度認めなくてはなりませんが、一方で廃棄物管理など下流段階だけでなく、生産・設計など上流段階も含めたライフサイクル全体をカバーする必要があるというのが日本の大方針です」(小林豪氏)
INC5.2では、日本は議長の要請を受け妥協案を探る役割を担いましたが、EUを中心とした厳しい規制の導入に積極的な野心派と、産油国を中心とした慎重派で意見は分裂。最終的に全32条中3条しか合意には至りませんでした。それでも必ずしも見通しは暗くはないと小林豪氏は述べます。
「会議終了後、関係国やNGOからは『国連の外で独自に条約を作っていく方がいいのではないか』といった声も聞かれました。確かに対人地雷禁止条約(オタワ条約)など国連の枠外で動くことで策定・発展した条約もありますが、世界中で日常的に使用される素材であるプラスチックに関しても同じようなプロセスで条約を作れるかは疑問を呈さざるを得ません。それに、今回は合意に至りませんでしたが、水面下の調整を続けたことで着地点が見えてきているという見方もあります。INCでは『一人で歩けば早く行ける。みんなで歩けば遠くまで行ける。』というケニアのことわざが何度も言及されてきました。この言葉のように、引き続き多くの国が参加できるような条約づくりを目指していきたいと思っています」(同氏)
サーキュラーエコノミー実現に向けたサラヤのチャレンジ
 サラヤの深澤恒正氏
サラヤの深澤恒正氏
続いては、洗浄剤や消毒剤の開発、薬液供給装置の開発等を手掛けるサラヤ株式会社における海洋プラスチックの有効活用や、自然循環に関する取り組みについて紹介がなされました。
環境への取り組みを事業の柱のひとつに掲げるサラヤでは、日本のなかでも海洋プラスチックごみ問題が大きな課題となっている長崎県対馬市と連携して、対馬に漂着した海洋プラスチックごみを回収・再資源化したものを原料として活用する挑戦を始めています。この取り組みの一環として、消毒ディスペンサーのコンセプトモデルを開発し、2025年大阪・関西万博で展示を行いました。
「消毒ディスペンサーは対馬で回収した海洋プラスチックと再生プラスチックを混ぜた素材から製作したものです。海洋プラスチックは洗浄して乾燥、粉砕、フレーク化してからペレット加工してプラスチック原料に戻す工程を踏んでいますから、通常のプラスチックと比べると多くの手間が掛かっています。製造には3Dプリンターを用いていますが、海洋プラスチックに付着した細かい砂や塩分をすべて取り除くことはできないため、一部の箇所では手作業に近い製造方法を取っており、荒い質感や形状になっている箇所もあります。それでも万博会場ではこのディスペンサーの製造背景を説明することで多くの方に海洋プラスチック問題を周知できましたし、そのなかから生まれた機器に対してポジティブな反応をいただけました」(深澤氏)
またサラヤは、同じく海洋プラスチックや、リサイクルされた漁網から作られたナイロン生地を素材に活用した「健康タイムマシン」も開発しています。これは現在の健康状態のチェックと未来の健康予測ができるというもので、こちらも万博会場で展示を行いました。
「万博に展示した機器はあくまでもコンセプトモデルという位置づけですが、これを機にサラヤの商品としての展開も考えています。もちろん海洋プラスチックごみを活用した製造は品質面でもコスト面でも難しい部分がありますが、この問題を取り巻く現状を知るからこそ、解決に貢献できるような研究開発をしていきたいと考えています」(同氏)
 サラヤの橋本典明氏
サラヤの橋本典明氏
さらにサラヤでは、サプライチェーン全体でサーキュラーエコノミーを実現するための取り組みも展開しています。その背景には、顧客からリサイクルや再利用の相談が増えていたことが関係しています。
「納入した使用済み洗剤容器をどうにかしたいというご要望が多く、メーカーでの回収やリサイクルができないか、資源ごみにできないかといったお声をいただいていました。しかし日本では産業廃棄物処理法によってプラスチックごみの回収には厳しい規制がかけられているため、リサイクルや再利用を行おうとしても回収や運搬のコストが大きくなり、いわゆる"逆有償"の状態になるという課題を抱えていました」(橋本氏)
そこでサラヤでは、次の3つの観点からこの課題に取り組みます。
(1)サーキュラーデザインの取り組み
洗剤を入れる容器そのものをリサイクル・分別しやすいように、統一性のある素材を活用してデザインを作り変えること
(2)顧客の協力の下での廃棄物処理
洗剤が付着したままでは資源回収できないため、容器の排出事業者である顧客によって一次洗浄を行ってもらい、専門業者に依頼して回収・運搬を実施
(3)自己循環システムの構築
グループ会社と連携してペレットからボトルを再成形して商品を充填し、再び顧客に納入する自己循環型システムを構築
「こうした動きは、私たち"動脈"分野の人間だけで取り組もうと思っても継続はできません。リサイクルのプロである"静脈"分野と連携し、その方々にもしっかりと対価が流れる仕組みを構築して継続的に取り組むことが大切になります。今後は法改正なども視野に入れつつ、より柔軟な対応や連携ができるようにしていきながら環境への取り組みを強めていきたいと考えています」(同氏)
サーキュラーエコノミー構築のハードルは何か
 写真左)小林光氏 写真右)吉高まり氏
写真左)小林光氏 写真右)吉高まり氏
講演を終えたところで、座長の小林光氏と副座長の吉高まり氏(一般社団法人バーチュデザイン 代表理事)、並びに参加者を交えた質疑応答へと移りました。はじめに小林光氏から「まずは枠組み的な条約を作り、細目は議定書にて補完する2段ロケット方式をとるやり方もありますが、なぜプラスチック条約は、条約自体で細目的なことを盛り込もうとしているのですか」と質問。小林豪氏は「もともとこの交渉では2024年末までに条文案の合意を目指すことが掲げられており、期限を意識するあまり条文に盛り込む必要がある事項と条約採択後に詰める事項との区別といったプロセスの組み立てが不十分なまま、一気に合意を目指そうとしていたという実情がございました。次に議論を再開する時は2段ロケット方式も含め、どのようなアプローチが適切なのかを改めて整理しながら着地点を探っていきたい」と答えました。
さらに小林光氏から「仮にプラスチック条約が成立しないと、どのような弊害が生じるか」という質問がなされます。これに対して小林豪氏と橋本氏は次のように回答しました。
「プラスチック汚染問題が地球環境や人体に及ぼす影響についての研究は増えていますし、社会的な注目度も高まっています。それに伴って一部の国や地域で独自のルールが作られ、イニシアチブを握ろうとする動きが加速することは避けられないでしょう。そうすると、対策をしている側としていない側の差は開いていく一方ですし、そうした状況から取り組みを始めるのではドラスティックな変化が強いられます。したがって、今の段階から各国が始めやすく段階的に強化できる条約を作ることが重要と考えます」(小林豪氏)
「条約がない場合、先進的な国や地域による高い視座でのルールだけで物事が進んでしまいますから、例えば突然高コストのものが流通し始める可能性などがあります。しかし国際的なルールが整備されれば均一化されたものが使用され、コストの高騰は抑えられる期待ができます。こうした点も条約のメリットではないでしょうか」(橋本氏)
吉高氏からは、「サーキュラーエコノミー構築のために他の企業や組織の巻き込みが必要ということだが、そのハードルとなるものは何か」という問いかけがなされ、橋本氏は「複合的な課題がある」と答えました。
「もともと日本ではごみを焼却するコストが低く済んでいましたし、街中から離れたリサイクル施設に運搬するコストは高くなります。また、事業系のごみは家庭から排出されるごみよりも洗浄や分別に手間がかかります。こうした取り組みを推進するために補助金を出すことなども考えられますが、一時的なインセンティブだけでは継続的な活動は難しいでしょう。このような複合的な課題があるなかで新しい企業と連携していくには、その企業や組織が高い志を持っていることが必要だろうと思っています」(橋本氏)
参加者からも積極的に質問が飛び交いました。例えばある参加者から「プラスチック汚染問題を解決するための資金をどう拠出していくことになるのか」との問いに、小林豪氏は次のように回答しました。
「INCではプラスチック製造国から徴収金を集めて対策に充てるという提案もありましたが、現実的には難しいでしょう。先進国が中心となって拠出する考えも勿論ありますが、従来の先進国と途上国の枠組みが今の経済状況には合っていません。したがって現実を見ながら交渉を重ねていかなければならないでしょう。ただ、プラスチック条約が成立しても日本で直ちに法改正につながる可能性は低いですし、当面は既に国内で行われている取り組みをしっかり継続するようなものになるでしょう。突然企業からお金を徴収して負担が増えるようなことは想定していないので、その点はご安心いただければと思います」(小林豪氏)
その他にも多くの質問があがり、2025年度最初のCSV経営サロンも、高い熱量に包まれていることが感じられました。最後に小林光氏は次のように挨拶を述べて、この日のセッションを締めくくりました。
「国際条約にはいろいろな役割があります。例えば科学的なデータを収集して新しい事実を見つけることもそのひとつです。そうやって新しいことを進めていると、必ず副作用や新たな課題が生じますが、それらをどう解決していくかが仕事の楽しい点でもあると思っています。冒頭で申し上げたように、皆さんが抱える課題を聞き、議論していくことが次への一歩になるでしょう。その意味で、今日はとてもいいお話を聞けましたし、今後もこうしたことをやっていきたいと思っています」(小林光氏)
 参加者からも多くの質問が飛び交った
参加者からも多くの質問が飛び交った
CSV経営サロン
2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。
2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。
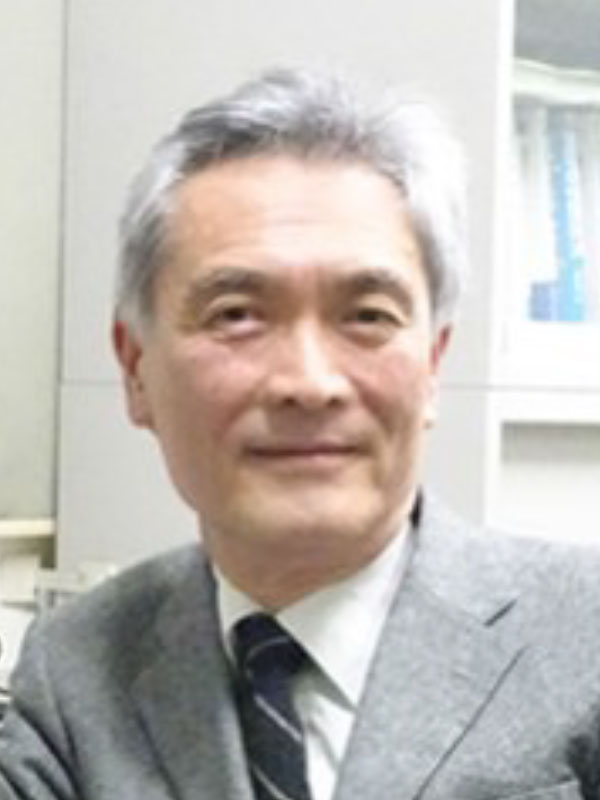
座長:小林光 氏
東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /
教養学部客員教授
慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。
1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。
慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。
再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏
一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /
東京大学客員教授/
慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。
IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。
おすすめ情報
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク
- 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 5
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 6
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 7CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」
- 8
 【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」
【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 - 9
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 10
 さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~
さんさんネットワーキング〜大忘年会2025~





