
イベント丸の内プラチナ大学・レポート
学校が変わる、地域が変わる、子どもが、大人が幸せになる「ウェルビーイングに重点を置く教育」とは
【丸の内プラチナ大学】Social SHIFT テーブルコース Day5 2025年1月31日(金)開催

4,8
未来志向型ビジネスや、新しい生き方・働き方を実践するソーシャルイノベーターと語り合う中で、ライフシフト、ワークシフト、ビジネスシフトのヒントを探る、丸の内プラチナ大学の「Social SHIFTテーブルコース」。最終回となるDAY5は、東京学芸大学教授、教育インキュベーションセンター長の金子嘉宏氏をゲスト講師に迎え、「ウェルビーイングに重点を置く教育」をテーマにお話しいただきました。
 Social SHIFTテーブルコース講師の石井綾氏(左)とゲスト講師の金子嘉宏氏(右)
Social SHIFTテーブルコース講師の石井綾氏(左)とゲスト講師の金子嘉宏氏(右)
未来の学びの場 みんなで創ろう。地域をワクワクする場所に
新しい学びの場の創造プロジェクト「Explayground」、学校の変革プロジェクト「未来の学校 みんなで創ろう。PROJECT」など、公教育のシステム変革の実践事業やSTEAM教育の推進に取り組む金子氏。冒頭、「学校」をテーマに取り上げ、こう話しました。
「学校には、教育・学びを提供する場としての機能と、コミュニティとしての機能の2つがあります。この中でも、今日は前者に焦点を当ててお話しします。中世の時代は、魚屋さんの子どもは魚屋さんになる、というように社会的位置が水平に移動することはあっても、垂直に移動することはほぼありませんでした。しかし、社会に出たら、誰もがなりたいものになれるようにしていくべきではないか。そのためには教育が必要ではないかということで、近代になると学校制度ができました。一定程度の知識や技能を子どもたちに身につけさせた上で、社会移動を可能にする公平性を担保すること。これが、学校教育の基本的な機能です。
ここで取り違えてはならないのは、義務教育とは、子どもにとっての義務ではなく、大人にとっての義務であることです。大人は子どもに教育を受けさせる義務を負っていて、すべての子どもは学ぶ権利を持っています。ですから、すべての子どもたちの社会移動を可能にするために、学校教育は全国の学校において、全員に対して公平に行われる必要があります」(金子氏、以下同)

次に金子氏が取り上げたのは、義務教育終了段階の生徒の学力です。2023年12月に公表されたOECDの国際学力調査(PISA)では、日本は科学的リテラシーで全参加国中2位、読解力で3位、数学的リテラシーで5位となり、いずれの分野でも世界トップレベルの学力であることが示されました。
「日本の学校教育は、学力をつけるという意味では非常にうまく機能していると言えますし、子どもたちが自ら進んで学んでいることは、社会に出てからも役に立つと思います。ただし、一定程度の学力が定着していない子どももいることや、「学びは楽しいか?」という問いに対するOECDの調査結果では、日本の子どもたちの評価が低いことも事実です。 こうした課題を踏まえ、現在文部科学省では、「個別最適な学び」の重要性が強調されています。個別最適な学びには、「指導の個別化」と「学習の個性化」という二つの側面があります。 「指導の個別化」は、一斉授業だけではなく、一人ひとりの学習進度や理解度に応じた指導を行うことで、誰一人取り残されることなく、一定の学力を定着させることを目指すものです。一方、「学習の個性化」は、子どもたちの興味・関心を起点とし、彼らが自発的に学びを深めていけるよう支援することを意味します。最初の問いも違えば、何を学ぶか、どこに到達したいのかも子ども一人ひとり異なるのが、「学習の個性化」です。 自分なりの問いを立て、主体的に学ぶことは、学びの基本なので、このような個別の学びを実現できたら素晴らしいと思います。しかし、学習指導要領という一定の枠組みの中で、学校教育において実現できるかどうかについては疑問が残ります」

続いて、金子氏は参加者に、「もし、あなたのお子さんが、学校から帰ってきてから3時間、カブトムシを見つめていたとしたら、何と言いますか」と問いかけました。
「『3時間もカブトムシをひたすら見つめるなんて、すごく主体的に学んでいますね』と言うと、保護者の方々は皆、うなずいてくれるのですがしばらくすると、『早く宿題しなさい』と諭してしまうのが現実です(笑)。お子さんとしては、せっかく主体的に学んでいるのに、勉強しなさいと言われてしまうわけです。この部分を伸ばしてあげることが、日本の子どもたちの学力は高いのに、なぜか学びを楽しんでいない、面白がっていないという問題の解決にもつながっていくのではないかと思います」
では、子どもたちは学校で主体的な学びを得ることができるのでしょうか。 残念ながら、「教える内容や時間数が定められた教科教育の中では難しい」といいます。教科や科目の枠を超えて、自分のやりたいことを学ぶ「総合的な学習(探究)の時間」はありますが、小中学校では年間70時間ほどしかありません。
「こうした状況の中、重要になってくるのが放課後の学びの場です。ここでは、子どもたちは主体的に学ぶので、指導者よりも伴走者が求められます。カブトムシの博士より、カブトムシを一緒に見つめてくれる大人がいてくれれば、それで十分なのです。人生100年時代といわれる今、大人にとっても、学び続けることが欠かせません。"学ぶ"と"働く"は、いわば両輪のように人生についてくるものといえるでしょう。だからこそ、子どもの学びを最大限優先しながら、地域の大人も一緒に学ぶ『開かれた学校』をつくり、活用していけるといいなと思います。折しも、各自治体では老朽化した学校の建て直しが検討されています。学校のあり方を変えていく70年に1回の大チャンスが到来しているといっても過言ではありません」

「最近、『大人も部活動をしましょう』とよくお伝えしています。週に2日でいいので、午後3時に仕事を終わらせて、自分の好きなことをする時間にあててみてはどうでしょうか。教員の働き方改革や少子化の影響により、部活動を学校から地域へ移行する動きが、多くの自治体で重要な課題となっていますが、大人も子どもと同じように部活動をすれば、地域移行はごく自然に実現できると思います。あともう一つ、皆さんにご提案したいのが『2.5%ルール』です。週に40時間働いているとしたら、その2.5%にあたる1時間をお子さんと遊ぶ時間に充ててみてください。親子で一緒に何かを創造しながら、大人も楽しく学び続けることができるのではないでしょうか」
そして「学びはそもそも面白かったはず」と金子氏は言い、参加者に再び問いかけました。
「じいちゃんも父ちゃんも漁師だし、自分も中学を出たら漁師になるけれど、二次方程式解けないとだめですか?」
これは、金子氏が岩手県山田町を訪れた際、地元中学校の校長先生が教えてくれた生徒からの問いです。校長先生は、何と答えてよいのかわからず、困ってしまったと話しました。
「ここでは2パターンの回答をご紹介します。1つ目は、『漁業もスマート化しないと生き残れないから、ちゃんと数学も勉強しておいた方がいい』。この回答の根っこにあるのは、『〇〇力をつけるために数学を学ぶ』というロジックで、学びを手段化しています。でも、もし数学者なら、全く違う答えが返ってくるでしょう。『二次方程式を解くのは面白いんだけどなぁ。面白いからやるじゃダメかなぁ』。この2つ目の回答は、学びが自己目的化しています。鬼ごっこをするうちに、コミュニケーション能力がつくかもしれませんが、コミュニケーション能力を身につけたくて、鬼ごっこをする子どもはいませんよね。遊び自体が自分の目的になっているから面白いのと同じように、学びも自己目的化することが大切だと思います。教育の観点から言えば、1つ目の回答は『教育の人材育成化』であり、2つ目の回答は『遊びを基盤とした教育』です。人材育成はもちろん大事ですが、遊びを創造する力や失敗する自由がある方が面白いですし、将来、日本の子どもたち全員がスーパーマンになる必要はないと私は思っています」

後半、金子氏は、遊びの本質、学校のハイカラ化と地域の学びのコモンズ化、超高度化テクノロジーによるリスクなどをテーマに取り上げ、参加者の皆さんに余すことなく知見を共有しました。
「テクノロジーの超高度化により人が生かされてしまう時代の生きる力とは、生きることを面白くする力だと思っています。自分が生きていることを面白くする力がないと、誰かの役に立つことだけでは人生の価値が見出せなくなる時がいずれ訪れるでしょう。この力をつけるためには、脱目的化し、学ぶことを自己目的化することが重要になってきます」
「皆さんは、動力付きの有人飛行を成功させたライト兄弟をご存じですよね。彼らが生きた時代の人々は、空を飛べなくて困っていたわけではありません。ライト兄弟は、純粋に空を飛んでみたかったのです。そして、飛行実験を繰り返していたら、いつの間にか人類初の動力飛行機の開発に成功し、それがイノベーションになったのです。
私たちも、人生と世界を味わい、誰かのために何かをクラフトすることを楽しみましょう。そして、自分の心が動くことをして、何か価値を生み出していきましょう。その二つが重なる部分を仕事にしていくことができたら、すごく幸せになれると思います。子どもたちと同じように、大人も『自分の好き』に挑んでいいのです。これからは成果主導ではなく、好きを駆動して何かやっていくうちに成果が出た、という風に考え方を変えていく必要があると思います」

金子氏の講義は、できたての美味しい食事をとりながら、くつろいだ雰囲気の中で行われました。
この日のメインディッシュは、金子氏がポートランドで食べ、感銘を受けたというミニハンバーグ料理「スライダー」。講義後は、今日の学びを参加者に体感していただくために、「カクテルづくり」が行われました。
「これは、STEAM教育を導入する際に子どもたちと行うワークです。普段、このワークでつくるのは、ノンアルコールカクテルですが、今日は大人の集まりですので、アルコールもご用意しています。カクテルづくりも、まずはありたい姿を描くことが重要です。自分が作りたいテーマをワークシートに書き込んでください。色んな材料を混ぜてみて、思い描いたものと違ったら、その原因を探ってみましょう。プロトタイピングをして、ブラッシュアップしていくことが肝なので、楽しみながら色々と試してみていただければと思います」
参加者は、「夕日」や「昭和レトロな光と影」など、思い思いのテーマでカクテルづくりを楽しみました。その後は、教育とChatGPTの未来、学校よりも家庭でデジタル化が進む理由、ティーチングとコーチングの違いなど、金子氏への質問が次々と上がりました。
学校が変わり、地域が変わり、子どもが、大人が幸せになる。そんな学びの場が地域に広がっていく未来はもうすぐそこまで来ているのかもしれません。今後のSocial SHIFTテーブルコースの発展に乞うご期待ください。
丸の内プラチナ大学
あなたの「今後ありたい姿」「今すべきこと」とは?
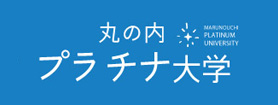
丸の内プラチナ大学では、ビジネスパーソンを対象としたキャリア講座を提供しています。講座を通じて創造性を高め、人とつながることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。
おすすめ情報
-

【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 石川県七尾市フィールドワーク
2025年11月7日(金)~9日(日)
-

【丸の内プラチナ大学特別連携講座】すさきがすきさフェス Vol.1 ~須崎市交流イベント 2025 in TOKYO~
2025年10月25日(土) 16:00~19:00
-

【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」
2025年11月5日(水) 15:00~18:00
-

【レポート】AI時代に求められるコミュニティマネジャーの価値と役割
丸の内コミュマネ大学~AI×コミュニティの未来~ 2025年7月10日(木)開催
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 3
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 4
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 5CSV経営サロン2025 第3回「資源循環の出口、有機性資源のアップサイクル」
- 6
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 高知県須崎市フィールドワーク - 7【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 北海道上士幌町フィールドワーク
- 8
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 9
 【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」
【FCAJ共催イベント】EMICoフォーラム2025 「産学官民の地域共創の場 イノベーションコモンズの現在地とこれから」 - 10
 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造
【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造

