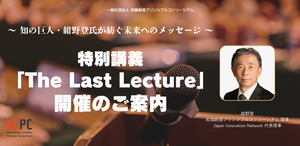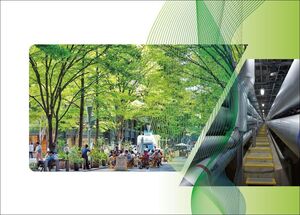複雑化する社会問題の解決への糸口がなかなか見いだせないなかで、多様な人びとが集い、未来志向で対話を重ねることを通じて変化を起こしていこうというフューチャーセンターが注目を集めている。6月7日から13日までの間、4回目となる『フューチャーセッション・ウィーク2014』が開催(会場:丸の内の富士ビル3F「3×3 Labo」)されるのに先立ち、主催の株式会社フューチャーセッションズ 代表取締役社長の野村恭彦さんに、フューチャーセンター、セッションの意義やフューチャーセッション・ウィーク(以下「FSW」という)のねらいなどについてうかがった。
組織でなく個人が主体のフューチャーセンター
-フューチャーセンターとはどういうものか、改めてご説明ください
 いま、世の中には解決すべき問題が数多くありますが、いろいろなところに縦割りの弊害が出ていて複雑な問題に対応できなくなってきています。少子化問題、高齢化問題がわかりやすいですが、その根っこはつながっているのに別々に手を打っている状況ですね。企業ではオープンイノベーションやコラボレーションも行われていますが、そこでアイデアが生まれても組織に戻って実行できないことが少なくありません。
フューチャーセンター、フューチャーセッションは、従来の発想を逆転するものです。つまりワークショップでアイデアを出して組織に戻すのでなく、自分たちで解決してしまおうというわけです。市民参加型の政治といえば、「市民の意見を議会や行政が受け止めます」というイメージですが、そうではなくて市民が主役になり、まちをつくる、問題を解決していく。そういう場がフューチャーセンターです。未来を創っていく主体が組織ではなく個人であるのがフューチャーセンターの特徴です。
いま、世の中には解決すべき問題が数多くありますが、いろいろなところに縦割りの弊害が出ていて複雑な問題に対応できなくなってきています。少子化問題、高齢化問題がわかりやすいですが、その根っこはつながっているのに別々に手を打っている状況ですね。企業ではオープンイノベーションやコラボレーションも行われていますが、そこでアイデアが生まれても組織に戻って実行できないことが少なくありません。
フューチャーセンター、フューチャーセッションは、従来の発想を逆転するものです。つまりワークショップでアイデアを出して組織に戻すのでなく、自分たちで解決してしまおうというわけです。市民参加型の政治といえば、「市民の意見を議会や行政が受け止めます」というイメージですが、そうではなくて市民が主役になり、まちをつくる、問題を解決していく。そういう場がフューチャーセンターです。未来を創っていく主体が組織ではなく個人であるのがフューチャーセンターの特徴です。
-社会問題を個人の力で解決していくのは難しくはありませんか?
個人には力がなく、組織にはあるというのはこれまでの論理です。個人にはものを感じることができる。個人が疑問を感じ、個人がなんとかしたいと思ったものを組織や専門家が応援して、一緒に実現するという大きな変化を生み出す仕組みがフューチャーセンターというわけです。
問題を提起して推し進めるのは強い意思
-フューチャーセンターでの対話がフューチャーセッションですね?
 そうですね。フューチャーセッションというのは、センターで行われる対話やアクションです。フューチャーセンターには、どのような課題を持ち込んでもいい。そこにはファシリテーターやディレクターがいて、「この問題だったら、こういう人たちが話し合ってアクションを起こしていけばどうか」という仮説を立てて、さまざまなステークホルダーを集めて、深い対話を通じて問題の本質を見極めて解決をめざしていくものです。
そうですね。フューチャーセッションというのは、センターで行われる対話やアクションです。フューチャーセンターには、どのような課題を持ち込んでもいい。そこにはファシリテーターやディレクターがいて、「この問題だったら、こういう人たちが話し合ってアクションを起こしていけばどうか」という仮説を立てて、さまざまなステークホルダーを集めて、深い対話を通じて問題の本質を見極めて解決をめざしていくものです。
フューチャーセッションで最も重要な役割を担うのは、「この問題をなんとか解決したい」という意思を持っている人。これまでのやり方では、たとえば認知症については、家族に認知症患者がいる人、介護・病院関係の人くらいしかこの問題に関心を持っていなかった。でも、「それでは問題は解決しない!」という意思を持った人が、これはまちづくりの問題だと広げる。認知症の人が買い物をするときに困らないか、移動するときはどうか、そこを解決していくことが本質ではないかと考えて、人脈をたどってステークホルダーを広げ、NPOや行政、企業など多様な人からなるコアチームをつくる。そのコアチームの人たちが自分のステークホルダーを集めていって、みんなで深い対話をする。そうすると、いままで自分事として深く考えてこなかったけれども、「自分たちが行動すれば何か役に立つかもしれない」と考える人が出てきて、主体者になる。そんな流れをつくる、問題を提起して推し進められる人が必要です。
別々の問題に携わる人びとをつなぎ、
ブレークスルーを生み出す
-FSWを始めたのはどういう経緯からですか?
 昨年も被災地で開催されたFSがあった。写真は岩手県大槌町「町づくりとしての観光事業きっかけは、東日本大震災です。震災直後に「我々はいったい何ができるだろう」というテーマでOST(オープンスペーステクノロジー)という対話を進めるなかで、私が「フューチャーセッションで日本の未来を考える1週間」というイベントを提案した。そして、震災から2ヵ月後の5月中旬に、1週間にわたり毎日セッションを実施したのがFSWの始まりです。連日50~100人が参加してくれて、その人たちが「こうやって未来をつくっていけるんだ」と仲間になったわけです。
昨年も被災地で開催されたFSがあった。写真は岩手県大槌町「町づくりとしての観光事業きっかけは、東日本大震災です。震災直後に「我々はいったい何ができるだろう」というテーマでOST(オープンスペーステクノロジー)という対話を進めるなかで、私が「フューチャーセッションで日本の未来を考える1週間」というイベントを提案した。そして、震災から2ヵ月後の5月中旬に、1週間にわたり毎日セッションを実施したのがFSWの始まりです。連日50~100人が参加してくれて、その人たちが「こうやって未来をつくっていけるんだ」と仲間になったわけです。
1年後、フューチャーセンターを増やしていくセッションを開いたところ、さまざまなセクターから120人が集まりました。行政、NPO、企業に政治家などがセクターを超えて対話してみて、「多くのことが解決できそうだ」とみんな感じた。だったら、みんなが自分の意思でセッションを開けば、いろいろな問題が解決するのではないかと。でも、それをばらばらにやっては、ほかで何をしているのかよくわからないので、それを可視化するためにまとめたのがFSW。2回目は、2週間で70くらいのセッションを実施しました。
-先ほど、フューチャーセッションで重要なのは意思を持った人というお話でしたが、FSWではそういう意思を持った人が集まってくるのですね
私は「日本にフューチャーセンターを1,000つくる」と宣言していますが、みんな必ず「フューチャーセンターをつくるのにお金がかかる」と言います。「そのROIは何か?」となるわけです。そうではなくて、「どんな問題を解決したい」「どんな未来をつくりたい」のか、なぜそれができないのかを本気で考える人間が必要だということで、「フューチャーセッションを設計・実践して未来を創れる人間を1,000人つくる」ほうが先じゃないかと。FSWにはそういう人を生み出す機能があります。
FSWは、たくさんのセッションを同じ場所で同時期に行いますから、互いに学びあえるでしょうし、違う意思で参加した人たちが別のセッションに参加することによって新しいものも生まれるでしょう。いままでは別の問題として、バラバラにやっていた人たちがつながって対話することで、互いが相手のリソースになり得ることに気づいていくことにも期待しています。
FSWでは、いろいろなアイデアが飛び出してきます。よくある切り口というのがあって、問題の当事者からはなかなかブレークスルーは起きないんですけれども、たとえば女性の活躍について、資生堂さんとプロジェクトを実施したとき、「どうしたら女性が活躍できるだろう」でなく、「どうしたら男性が輝いていけるのか」を考えてみたらどうか、というアイデアが出てきました。組織のなかで男性は輝いていない。男性がもっと輝いていれば女性が活躍できるようになるんじゃないかというんです。このように、問題の構造を変えていく、接点を変えていく発想は、その問題の外様が持っていたりする。そういうことがたくさん起きるのがFSWです。
企業人の参加で新しいものが生まれる?
FSWが丸の内で開催される意義
-FSW2014では、どのようなことが話し合われるのでしょうか?
 昨年のFSWの様子がサイトでレポートされている。興味のある人はこちらも読んでみよう。今回のFSWでは「2020年、世界に示したい日本」をグランドテーマに掲げています。2020年は東京オリンピックの年で、経済の活性化という文脈で語られがちですけれども、それは昔の日本をイメージさせます。そうではなくて、私たちは、震災を経験して都市機能がいかに脆弱なものか、そして政府に頼っていてもうまくいかないことがわかり、自分たちの手でまちをつくりなおしてきた。そういう日本が「これからこういう社会をつくっていく」ということを世界に示したい。日本らしいアプローチ、新しい視点などいくつものアウトプットを出していきたいと思います。
昨年のFSWの様子がサイトでレポートされている。興味のある人はこちらも読んでみよう。今回のFSWでは「2020年、世界に示したい日本」をグランドテーマに掲げています。2020年は東京オリンピックの年で、経済の活性化という文脈で語られがちですけれども、それは昔の日本をイメージさせます。そうではなくて、私たちは、震災を経験して都市機能がいかに脆弱なものか、そして政府に頼っていてもうまくいかないことがわかり、自分たちの手でまちをつくりなおしてきた。そういう日本が「これからこういう社会をつくっていく」ということを世界に示したい。日本らしいアプローチ、新しい視点などいくつものアウトプットを出していきたいと思います。
-今回は、丸の内の「3×3 Labo」で開催されますね
ある意味で、それは象徴的なことです。丸の内という日本のど真ん中で、多くの企業人が参加して、働き方やCSR、まちづくり、東京と地域の関係などを真剣に議論するということですから。これまでの社会の仕組みを守ってきた人たちが、新しい社会の仕組みをつくる場に参加するわけですね。まだ会社や行政が舵を切るには、新しいシステムが脆弱で不安ですよね。そこに個人として参加することによって、自分のなかの多様性に気づき、いまの組織と新しいやり方に接点を見つけられたらいい。次の6年間で、私たちがどう新しい仕組みをつくっていけるのかを、日本を支える組織の内部からみなさんが考えていくことにつながればいいですね。
たとえば、エコッツェリアさんの「CSRイノベーションワーキンググループ」に参加されているCSR担当者のみなさんと、会社の現場で働く人たちが集まって、働き方を考えるというのは面白いのではないでしょうか。CSR担当の人たちというのは、会社の真ん中でそこで働く人たちの働く意義をつくっている。いちサラリーマンとして働いている人たちの「自分はもっと社会に貢献できる仕事を会社のなかでやりたい」というパワーと、CSRの担当者が持っている目的を見つけるパワーがつながれば、「個人が働き方を変えること」と「企業が社会的責任を果たすこと」がもっとダイレクトにつながるのでなないかと思います。
-「興味はあるけど、強い意思は・・・」という人も参加してもらいたいですよね
もちろんです。まずは参加してみるのが入口。対話で世の中を変えていくことに少しでも関心がある人は、まずいろんなセッションに参加してほしい。普段付き合っていない人たちと出会えるので、そこで自分の考えを語り、「今度こんなことをやりたい」と言えば、みんな来てくれると思うんですよ。ウィークの後半に自分のセッションを企画しておいて、その前にいろいろセッションに参加して仲間をつくって来てもらう手もあるかもしれない。まずやってみようと決めて、困ったら周りが助けてくれますから、そんな気持ちでチャレンジしてほしいですね。
-フューチャーセッションを通して、どのような未来を創っていこうとお考えですか?
社会問題は解決できるかどうかだけに意味があるのではなく、解決に向かってみんながアクションを起こすことに意味があると考えています。自分が解決したいことができたからと言って本当に社会がよくなるのかはわからない。いま子どもの創造性が足りないといって創造性の教育を一生懸命やったら、次には違う問題が出てくるかもしれない。問題の解決を目的化してしまうと、社会にとって一番よいかどうかわからないことをやってしまうかもしれません。常に何が正しいのかを問い続けていくことが大切です。
私は、社会問題の究極の解決は、市民全体の考え方が転換することだと考えています。その問題に関心のある人がやって「一丁上がり」というのではなく、その問題にみんなの注目を集めて、別の人たちが関心のある問題につなげて、どんどんステークホルダーを広げていって、気がつけば「その問題ってこう考えるのが当たり前だよね」と社会全体が変わる。そんなソーシャルイノベーションの起点になれたらいいなと思っています。

野村 恭彦(のむら・たかひこ)
株式会社フューチャーセッションズ代表取締役社長、金沢工業大学教授(K.I.T.虎ノ門大学院)、国際大学GLOCOM 主幹研究員、博士(工学)
慶應義塾大学大学院修了後、富士ゼロックス株式会社入社。同社の「ドキュメントからナレッジへ」の事業変革ビジョンづくりを経て、2000年に新規ナレッジサービス事業KDI(Knowledge Dynamics Initiative) を立ち上げ。2012年6月、企業、行政、NPOを横断する社会イノベーションをけん引するため、株式会社フューチャーセッションズを創設。著書に「サラサラの組織」(共著)、「裏方ほどおいしい仕事はない」、「フューチャーセンターをつくろう」、監訳に「コミュニティ・オブ・プラクティス」、「ゲームストーミング」、「コネクト」、「シナリオ・プランニング―未来を描き、創造する」など。つくりたい未来は、市民自らが対話し実行する創意形成社会。
おすすめ情報
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日