

従業員の健康や環境への配慮など、オフィスに期待される機能は多様化し、高度化している。大丸有やその近辺のエリアでも、KITTEや大手町タワー、茅場町グリーンビルなど、個性的なオフィス空間が次々に誕生。自由で独創的なオフィスは、イノベーティブな製品やサービスを生み出す可能性に満ちあふれている。一方で、生産性や効率性の追求へのニーズは高く、オフィス空間の良し悪しが経営に直結すると言っても過言ではない。オフィスに求められる価値とは? そして進化の行方は? オフィス製品やシステムの開発・提供からコンサルテーションまでを手がける2社の挑戦を通じて、新たな段階に入ったオフィスづくりの最前線を紹介したい。
次世代型のオフィス空間はすでに登場している
「オフィス」という言葉を耳にして、多くの人はデスクや椅子、キャビネットなどが整然と並ぶ空間を思い浮かべることだろう。天井の蛍光灯の下で社員たちは横並びにパソコンの画面を眺め、日々の作業を黙々とこなしていく。しかし、このようなイメージは、企業とそこでの働き方が大きく変化した今、もはやひと昔前のものだ。最新のオフィスには、社員の健康や環境面に配慮しつつ、知的生産性を向上させるためのさまざまな工夫が凝らされている。
そのような視点に立って、次世代型のオフィス空間を実際の場として提案している施設がすでにある。その一つが、大手オフィス家具メーカーのコクヨファニチャーを含むコクヨグループが国内19ヵ所と上海やシンガポールなど海外に展開している「ライブオフィス」だ。
「人」が中心の場をめざし試行錯誤
 コクヨのエコライブオフィスでは、一部の社員は好きな場所で仕事をしている。天井の照明と空調はモジュール化され、人感センサーで制御されている
コクヨのエコライブオフィスでは、一部の社員は好きな場所で仕事をしている。天井の照明と空調はモジュール化され、人感センサーで制御されている
コクヨのライブオフィスは、同社の社員が実際に働く光景を見ることができる画期的な施設だ。大阪に第一号ができたのは1969年というから驚かされる。「オフィスが抱える課題を解決する提案を家具や内装を中心に行うとともに、人を中心にしたオフィス空間づくりのヒントになればと考えて開設しました。設備やレイアウトは、データやお客さま、社員の声を受けて常に改善を図っています」(広報コミュニケーション部課長・海老澤秀幸さん)。
なかでも品川オフィス5階のワンフロアにある「エコライブオフィス品川」は、働きながらオフィスを環境と健康に優しいものへと変えていくことをめざす実験空間だ。2008年11月に開設した。新規事業開発室シニアプロデューサーの飯沼朋也さんは、そのコンセプトを次のように話す。
 飯沼朋也さん。「屋外で働くなど、新しいワークスタイルの選択肢を提案していきたいですね」と話す
飯沼朋也さん。「屋外で働くなど、新しいワークスタイルの選択肢を提案していきたいですね」と話す
「地球温暖化などの環境問題に対応して省エネや節電を進めていく際、従来は社員にコスト削減などの『我慢』を求めるエコが主流でした。それも大事ですが、オフィスで働く『人』を中心に据えて、その意識を変えてもらいエコ活動につなげていくほうが、より創造的で効率よく取り組めると考えたのです」。
フロア内でひときわ目を引くのが、「ガーデンオフィス」だ。ビルの谷間に突如現れるこのオープンスペースには、テーブルや椅子、傘などが用意されている。「仕事は部屋の中でするもの」という常識を覆し、社員は太陽の下で季節の風を感じながら、植栽や池の傍らで作業することができる。
 ガーデンエリアのような屋外での作業は、社員の創造性やエコ意識を醸成する。バッテリーなどのサポートグッズも豊富に「ずっと室内でデスクに向かっていては新鮮な発想が生まれにくい。屋外で働くことは健康によいですし、照明や空調もいりません」(飯沼さん)。年間数十日近くガーデンオフィスで執務した人もいるなど、社員からも好評だ。
ガーデンエリアのような屋外での作業は、社員の創造性やエコ意識を醸成する。バッテリーなどのサポートグッズも豊富に「ずっと室内でデスクに向かっていては新鮮な発想が生まれにくい。屋外で働くことは健康によいですし、照明や空調もいりません」(飯沼さん)。年間数十日近くガーデンオフィスで執務した人もいるなど、社員からも好評だ。
もちろん外では陽射しや風が強い日もある。社員のガーデンワークをサポートするため、バッテリーや日除け、クッションなど屋外で快適に作業するためのグッズもある。
また、ガーデンに面した「スタジオ」は、社内外の人が会議やセミナー、研修などを行うエリアだ。照明は必要な分だけつければ十分。外気温をセンサーで感知して自動開閉する換気窓により、自然空調も実現した。
ガーデンとスタジオの奥へ進むと、コクヨ社員の働く「オフィス」エリアが現れる。社員が好きな場所で仕事ができる、単なるフリーアドレスでなく、さまざまな形や高さのデスクによってコミュニケーションがとりやすいよう配慮されている。
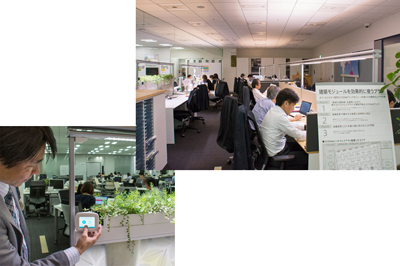 オフィスエリアでは、照明はタスク&アンビエント方式を一部採用し、手動で照度や色温度を調整することもできる
オフィスエリアでは、照明はタスク&アンビエント方式を一部採用し、手動で照度や色温度を調整することもできる
建築設備の照明と空調は、人感センサーで人のいるところを中心にオンにし、不在の状態が続くとオフにしたり照度を低くしたりする。一方で、デスクまわりや会議スペースなど一部の照明は手動でも調整でき、社員が自分の意志でオフィス内の環境を制御できるようにする工夫が随所に見られる。
最新設備の導入と、残業をなくすなどワークスタイルの改善を続けた結果、年間のCO2排出量を初年度で44%削減して当初目標を見事クリア。2011年の削減率は55.5%に達した。
 「『結の森』は、木を利用して成長してきたコクヨの、いわば森への恩返しです」と話す加賀谷廣代さんオフィスの一角には明かり取りの天窓が設けられ、木や下草が育つ隣で社員がノートPCを開いて作業する。
「『結の森』は、木を利用して成長してきたコクヨの、いわば森への恩返しです」と話す加賀谷廣代さんオフィスの一角には明かり取りの天窓が設けられ、木や下草が育つ隣で社員がノートPCを開いて作業する。
また、多くの家具には適正に管理された森から生まれたFSC森林認証の間伐材が使われている。「四万十の旧・大正町森林組合(現・四万十町森林組合)と協力して『コクヨ-四万十・結の森プロジェクト』を2006年に立ち上げ、間伐材の製品化に取り組んでいます」。環境事業TCMタスクで森林・木材コーディネーターを務める加賀谷廣代さんはこう話す。
- 続きを読む
- 外と内の「知」が交わる共創型の創造拠点も登場
外と内の「知」が交わる共創型の創造拠点も登場
 イトーキの「SYNQA」1階にある「Work Café」は、外部の人同士が交流することのできる自由な場だ一方、これからのオフィス空間のあり方を社会へ提案する最新の施設が、2012年11月に東京・中央区にオープンした。同じくオフィス家具大手のイトーキによる、「イトーキ東京イノベーションセンター『SYNQA(シンカ)』」だ。
イトーキの「SYNQA」1階にある「Work Café」は、外部の人同士が交流することのできる自由な場だ一方、これからのオフィス空間のあり方を社会へ提案する最新の施設が、2012年11月に東京・中央区にオープンした。同じくオフィス家具大手のイトーキによる、「イトーキ東京イノベーションセンター『SYNQA(シンカ)』」だ。
「協業パートナーと弊社がSynchronize(同調)して、Win-Winの関係を保ちながら新しいビジネスを生み出して進化していくことを表現しました」。ソリューション開発統括部・カスタマーリレーション戦略企画室室長の町田年英さんは、「SYNQA」という名前に込められたコンセプトをこう語る。 書籍などの資料とデジタルの融合について話す町田年英さんオープン以来、2万人を超える人が来館したという。
書籍などの資料とデジタルの融合について話す町田年英さんオープン以来、2万人を超える人が来館したという。
「SYNQA」は、イトーキにとって東京の出発点である京橋に建つ商業ビルの3フロアを占める。同社がこの施設を「事業創造拠点」と位置づける理由を、FMデザイン設計部副部長の二之湯弘章さんに聞いた。
「『SYNQA』は、企業外部の『知』と内部の『知』を交流させて新たな価値創造につなげていく、まさにオープンイノベーションを形にした施設です。従来型のショールームと違い、さまざまなステークホルダーが集い、交流を図れる一方で、組織の生産空間としての機能も持ち合わせ、かつ高い発信力を備える場をめざしました」。 二之湯弘章さん。「外と外、外と内、内と内がそれぞれ交流し、価値の創造へとつなげていける場。それが『SYNQA』です」と語る
二之湯弘章さん。「外と外、外と内、内と内がそれぞれ交流し、価値の創造へとつなげていける場。それが『SYNQA』です」と語る
「SYNQA」は、主に組織の「外」と「内」との関係性の視点からデザインされている。1階の「Work Café」は「外」と「外」が交流する場で、ビジネスにかかわるあらゆる人に開かれている。広い木質空間にカフェとステージ、会員制のサテライトオフィス、そしてライブラリーがあり、すべてオープンスペースになっている。
ライブラリーでは書棚の本と壁の大型モニター、そしてテーブル上のタブレット端末が連動しており、利用者は興味や関心のおもむくままに情報を見つけ、手に取って楽しむことができる。
2階の「Team Lab」は、社内外の交流から得られた知を新たな発想に昇華させるとともに、情報の共有と発信を行う、いわば「外」と「内」が交流する場だ。 2階の「Team Lab」(上)は、1階で得た外の「知」を新たな発想に育てて3階の「SYNC OFFICE」(下)につなげるための部屋やブースなどを完備している
2階の「Team Lab」(上)は、1階で得た外の「知」を新たな発想に育てて3階の「SYNC OFFICE」(下)につなげるための部屋やブースなどを完備している
展示会やプレゼンテーションなどを行えるプロジェクトルーム・ブースのほか、独創性を高めるインキュベーション・サロン、セミナールームなどが用意され、シアターや資料館もある。
そしてイトーキ社員が働く3Fの「SYNC OFFICE」は、「内」と「内」が交わるハイブリッド・アドレス・オフィスだ。まさにオープンイノベーションをつくっていく人間が働き、生まれてくるオフィスであり、ワーキングショールームとして見学も受け入れる。
「スタッフは基本週4日、フリーアドレスの『NIWA』と呼ぶソロワークスペースで作業しますが、週に1日は組織定住スペースの『CAMP』に集まり、チーム内の交流を深めています」(二之湯さん)。
 「オフィスで直接多くの社員と話せるので、メールよりスピード感がありますね」と話す岡田直之さん実際に働いている社員はどう感じているのだろうか。営業本部ソリューション営業部でアカウントマネージャーを務める岡田直之さんは、コミュニケーションのスピード感が増したと話す。「営業職は外回りが多いので、オフィスにいる時は短時間で各部署の社員とコミュニケーションをとる必要があります。ここはオフィス自体が回廊式のつくりになっていて、一周まわる間に多くの社員と話をすることができます」。
「オフィスで直接多くの社員と話せるので、メールよりスピード感がありますね」と話す岡田直之さん実際に働いている社員はどう感じているのだろうか。営業本部ソリューション営業部でアカウントマネージャーを務める岡田直之さんは、コミュニケーションのスピード感が増したと話す。「営業職は外回りが多いので、オフィスにいる時は短時間で各部署の社員とコミュニケーションをとる必要があります。ここはオフィス自体が回廊式のつくりになっていて、一周まわる間に多くの社員と話をすることができます」。
個別の会議室をつくらずオフィス自体をコンパクトにできる点や、ペーパーレス化が進むことも魅力だ。
オフィスの進化は止まらない
最新施設を見学してわかったのは、新しい機器やシステムを導入するだけで理想のオフィスは生まれないということだ。
たとえば現代のオフィスでは、社員が個々のデスクを持たず好きな場所で仕事ができるフリーアドレスはもやは珍しいものではない。次世代型オフィスにおけるワークスタイルの大部分がフリーアドレスを前提としており、無線LANをはじめとする最新の設備機器を備えている。
その一方で社員同士顔を合わる時間が減り、仕事を一人で抱える傾向が強くなる。企業としても、社員の心身両面についてのケアが行き届かなくなる懸念がある。両施設ともこの点を強く意識しており、コミュニケーションスペースや時間を設けるなど、組織としてのチーム力を高めるためのアイデアを盛り込んでいる。
 NEXT OFFICEのシェア・フラットオフィス空間はこの先どのように進化していくのか。その答えの一つを、コクヨファニチャーが2012年12月にリニューアルオープンした「霞が関ライブオフィス "NEXT OFFICE"」に見ることができる。「NEXT OFFICE」と名付けられたこのオフィスは、社内の連携を深める「深輪(しんりん)」と、社外との人とつながる「広縁(こうえん)」をコンセプトとしている。
NEXT OFFICEのシェア・フラットオフィス空間はこの先どのように進化していくのか。その答えの一つを、コクヨファニチャーが2012年12月にリニューアルオープンした「霞が関ライブオフィス "NEXT OFFICE"」に見ることができる。「NEXT OFFICE」と名付けられたこのオフィスは、社内の連携を深める「深輪(しんりん)」と、社外との人とつながる「広縁(こうえん)」をコンセプトとしている。
「変化に対応しながら違いを生み出す『強いチーム』をつくるため、ICTツールとクラウド技術をフル活用して時間や場所に制約されない働き方とコミュニケーションをめざしました」(コクヨ・海老澤さん)。
同年4月には渋谷ヒカリエにメンバー制オフィス「MOV」も開設しており、ワークスタイルの変化に対応した社会への提案を戦略的に行っている。
企業の成長と経営課題解決を至上命題にしつつ、社員のワークスタイルを主軸に据えたオフィス空間。その実現には、組織と社会の未来を見据えて、オープンイノベーションと強い組織を両立できる空間をプロデュースしていく理念と仕掛けが必要だ。
おすすめ情報
-

【Viva Málaga!】スペイン・マラガの知られざる魅力
#5 スペイン南部に根付く日本の絆――アンダルシアで活躍する日本人と特別な村
-

【さんさん対談】「本当の意味で良いことを」開拓精神が育んだ自他尊重のマインド
八木橋 パチ 昌也氏(日本アイ・ビー・エム株式会社コラボレーション・エナジャイザー)×田口真司(3×3Lab Futureプロデューサー)
-

コンビニ飯でも大丈夫?!ビジネスパーソンのパフォーマンスアップの食事選びBusiness Person Wellness Seminar vol.2
2023年7月21日(金)18:30-19:30
-

ビジネスパーソンのパフォーマンスを上げる快眠法則 Business Person Wellness Seminar vol.1
2023年7月7日(金)18:30-19:30
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2024年度開講のご案内~第9期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー
【大丸有シゼンノコパン】大手町から宇宙を「望る(みる)」ービルの隙間からみる、星空の先ー - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク
【丸の内プラチナ大学】逆参勤交代コース 壱岐市フィールドワーク - 5
 【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季
【大丸有シゼンノコパン】【朝活】大丸有で芽吹きを「視る(みる)」ー春の兆しは枝先からー/まちの四季 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2024年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜
【レポート】遊休資源が輝く未来へ 〜山形に学ぶ持続可能な地域づくりの挑戦〜 - 8
 フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~
フェアウッド×家具~ものづくりを通じた自然や生態系への貢献~ - 9
 指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感
指導経験ゼロから日本一のチームを作った「日本一オーラのない監督」が語る存在感と自己肯定感 - 10
 【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日
【大丸有フォトアーカイブ】第2回 みんなの写真展 2月21日~3月4日

