

「CSV経営サロン」では、「環境」をひとつの軸としつつ、社会問題の解決をどうビジネスにつなげていくか、検討を続けてきました。2011年からスタートして7年目となる今期のテーマは、「東京オリンピック・パラリンピック(以降オリパラ)」と「持続可能性」、「SDGs」についてです。
第3回となる本サロンでは、オリパラ関連の報告に加え、地球環境と人々の暮らしを持続的なものとするためすべての国連加盟国が2030年までに取り組む目標である「持続可能な開発目標(SDGs)」の17の分野のうちから、7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに(エネルギー問題)」、12「つくる責任・つかう責任(資源)」というテーマをピックアップして議論が交わされます。
第1回 http://www.ecozzeria.jp/events/csv/csv20170713.html
第2回 http://www.ecozzeria.jp/events/csv/event171220.html
なお、今回は"道場主"、主宰者・小林光氏(エコッツェリア協会理事、慶應義塾大学大学院特任教授)が米国での教鞭のためやむなく欠席。"道場主代理"として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のクリーン・エネルギーファイナンス部主任研究員、慶應義塾大学大学院政策メディア研究科特任教授の吉高まり氏が、進行を務めます。また、プレゼンターの方々の他、アドバイザーとしてValue Frontier株式会社取締役、梅原由美子氏も加わり、議論を深めていきました。
企業価値の評価基準としてSDGsが活用されている

最初のプレゼンテーションは、東京オリパラに関する内容と、近年の金融市場のトレンドについてです。吉高氏がマイクをとりました。
「東京オリパラまで3年を切りましたが、環境対策は現在残念ながら危機的状況にあります。持続可能性の整備についてもあまり進展が見られず、このままでは世界に誇れるオリパラにはならないでしょう」
現状にこのようにくぎを刺したあと、吉高氏が語ったのは、SDGsを取り巻く金融環境の変化についてでした。
「私の専門であるファイナンスに関して、大きな波が来ています。世界市場のトレンドは、ESG投資。環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)という、財務諸表には表れない"見えない価値"に着目して投資先を選ぶ動きが加速しています。ESG投資は世界の資産運用の3割に迫る勢いで成長し、日本でも取り入れる動きが相次いでいます。日本では2014年に、安倍総理がESG投資の積極化に言及し、その後、年金積立金管理運用独立行政法人がESG投資を推進。日本の年金資産は100兆円以上で、世界一の規模です。その巨額資金の恩恵に預かるため、企業側としてはESGに力を入れていく必要があります。そして、企業の財務部はESG投資の統合評価においてSDGsを活用するようになってきています。特に今回のサロンのテーマである"エネルギー"と"資源"に関して、より重要視する姿勢が顕著です。つまり、企業価値を測る際には、これまでのような財務指標分析およびガバナンス分析に加え、環境や社会に対する在り方という新たな軸が加わってきているのです」
そうした流れを受け、日本でも再生可能エネルギーや、環境、資源などに企業の目が向きつつありますが、まだまだ十分とはいえないよう。
「例えばアップル社は、サプライチェーンのすべてで再生可能エネルギーを使うことを目標にしていますが、達成率は96%でとどまっています。再生可能エネルギーを使えない、残りの4%はどこかといえば、実は日本のサプライチェーンです。エネルギーコストが高すぎて、日本でだけ実現できないのです」
東京オリパラででる1日300トンのゴミをどうするか
続いて、ゲストによるプレゼンテーションがスタートしました。
 最初に登場したのは、里山エナジー株式会社代表取締役、大津愛梨氏。熊本県で無農薬の米を生産する専業農家という立場から、食料とエネルギー問題について語ります。
最初に登場したのは、里山エナジー株式会社代表取締役、大津愛梨氏。熊本県で無農薬の米を生産する専業農家という立場から、食料とエネルギー問題について語ります。
「うちでは赤牛を20頭飼育していますが、米を収穫した後の藁で育てています。そして、牛たちの糞がまた田んぼを豊かにして、実りへとつながる......。そうしてうまく土地を利用することが、日本の循環型社会の在り方であると感じます。今後の食糧の自給は、大規模農家だけでは厳しくなります。私たちのような自給的農家のコミュニティが残っていくことが、日本社会にとっても必要なのです」
大津氏は、15年ほど前からブログを更新し、農家の仕事や自らの思いを発信し続けてきたといいます。そうした中で起きたのが、2016年4月の熊本地震でした。
「地震があって気づいたのは、エネルギー循環型の農家というのは、災害に強いということです。水源も近く、電力も再生可能エネルギーを使っていたことで、ライフラインが寸断された中でも、生きるのに必要な食べ物とエネルギーを確保できました。農家のレジリエンスの高さを改めて感じました」
ただ、そうしてエネルギーを自給しているような農家や農村の数が少ないのが問題である、と大津氏は指摘します。
「例えばドイツでは、バイオエネルギー村が1000か所になろうとしています。家畜の糞尿からバイオガスを作り、電気を売電し、熱は町中に巡らせた配管に温水を流す"暖房"に利用するというような形で完全自給自足をしている村もあります。私も、農家でエネルギーを作り、自給自足を実現したくて、里山エナジー社を立ち上げました。農作物とエネルギーを合わせて作る。まだ小さな規模ですが、これからもやっていきたいと思っています」

続いてのゲストは、株式会社市川環境エンジニアリングの萩野谷学氏と佐藤弘氏です。
まずは萩野谷氏から、市川環境エンジニアリングがどのような会社なのか、事業概要の説明がありました。
「1971(昭和46)年の設立で、浄化槽を作る事業から始まりました。現在は、環境ソリューション事業として、産業廃棄物事業、バイオマスなどのエネルギー事業、プラスチックなどの資源リサイクル事業、自治体のリサイクル施設の維持管理などを手掛けています。排出事業者などとも提携し、高度なリサイクル社会の実現を目指している会社です」
ここで佐藤氏にバトンが引き継がれ、同社が行う「東京オリパラへの提案」についてのプレゼンテーションがありました。
「オリパラでは、選手村やプレスセンターなど約50の関連施設があります。開催期間中には、そこから一日300トンを超えるごみが出るというのが私たちの試算です。それに対応するための提案をオリパラの組織委員会に提案しています」
具体的な提案内容は、以下の通りです。
・3R(リデュース、リユース、リサイクル)のもと、全競技施設、関連施設の環境目標を統一する
・ごみゼロを目指し、全競技施設、関連施設の廃棄物を統合して管理する
・大イベントならではの廃棄物発生量の予測、対策を実行する
・NPOボランティアとの連携による運営を行う
・世界のモデルとなり得る都市型再生エネルギー(バイオガス、水素等)事業の実現のきっかけとなるイベントとする
「一方で、課題もあります。もっとも難しいのは、費用をどうするかです。イニシャル、ランニング、ライフサイクルコスト......。それらをどこが負担するのか、なかなか固まらないでしょう。その他、リサイクルステーションの設置場所の確保や認可、オリンピック核施設との連携のやり方など、解決すべきことがいくつかあり、今後も取り組んでいきます」
やや難しいディスカッションテーマに参加者が挑戦

ここから、いよいよ参加者とのディスカッションに移ります。
まずは吉高氏より、二つのディスカッションのテーマが発表されました。
①企業の脱炭素への動きなどを踏まえ、地方における地産地消の再生可能エネルギーを促進するためにはどうしたらいいか
②循環経済、ゼロエミッション経済の日本での今後の可能性は?必要なもの、キードライバは何か
参加者は5~6人のグループに分かれ、各テーブルで課題を検討し、テーマに沿って話し合っていきます。
「結局は国が動きださねば進まない」「企業と農村、デベロッパーと住人がかみ合わないとうまくいかない」「住民との合意形成が鍵」「都会と田舎、共通の価値観が必要ではないか」......さまざまな意見が交わされ、どのテーブルでも熱い議論が行われていましたが、今回のテーマはなかなか難しく、時間内に結論を導くことが難しかったようです。

その後は、各グループの意見をひとつに集約した上、代表者が発表しました。
主だった内容と吉高氏の回答を要約します。
発表者「テーマ①に関して、地域住民といかに合意し、事業者が地域と一緒に汗をかいていくかが重要だという意見が出た。熱い思いは大切だが、それだけでは普及は進まない。どう実利を持たせるか。そのための鍵は、地域の金融機関が握っているのではないか、というところでタイムアップとなった」
吉高氏「地域密着型の金融機関は重要なプレーヤー。彼らに対し、積極的に情報を発信して知識を正しく理解してもらった上で、普及のために動いてもらえる状況を作れるといい」
発表者「テーブルのメンバー全員が製造業の関係者であり、議論の内容をテーマ②の循環経済に絞った。製造業の現場では、設計者や開発者が努力して耐久性やリサイクル性を高めた製品を作っている。しかし消費者がその機能を使いこなすことができなければ、効果は半減してしまうため、消費者への啓もうが必要であると考える。工場においては、100%再生可能エネルギーを使うのは現状では難しい。法律ができない限り、価格にも転化できないのではないか」
吉高氏「消費者への啓もうが大切というのは大いにうなずける。例えば国土交通省が『エコレールマーク』を作って、環境に優しい貨物鉄道輸送で運ばれたものだということを一般消費者にアピールしている。再生可能エネルギーでもそうした啓もう活動が必要だろう」
発表者「①に関しては、結局は補助金がなければ採算が合わなくなって事業が続かない。事業として継続性を持たせることが重要だと話し合った。また、村や町単位より小さなコミュニティの中でも自給自足を考えてもいいのではないか。例えば、会社に発電ができるサイクリングマシンを置き、健康に運動しつつエネルギーを作る、というような」
吉高氏「持続性というのは大きな課題のひとつであり、そのアイデアを考え続けていってほしい。そして、これからはより小さなレベルでの自給自足もまた、社会に必要となるものだと感じる」
環境と金融をつなげるものが、もっと出るといい

白熱のディスカッションが終わった後には、改めて講師陣からの総評がありました。
萩野谷氏「これだけいろいろな意見が出るのは素晴らしいことです。私たちのような業者は、認可がなければビジネスができません。日本の企業は素晴らしいリサイクル技術を持っているのに、許可や認可という壁に阻まれているケースも多いと感じます。個人的には、もっと認可のおりやすい環境になれば、リサイクル事業がさらに促進されると感じています。
大津氏「この場ででてきている意見、価値観が、私たち地方の在り方に直結していくと思います。まずはアイデアをたくさん考えていくことが大切ではないでしょうか」
梅原氏「私は企業のコンサルティングをしていて、東京と地方を行ったり来たりしていますが、大津さんは農業の抱えている危機感を前向きに訴えている姿勢が素晴らしいです。みなさんもここでの話をそのままにせず、アイデアを地方の人とどうシェアしていくかを考えて欲しいと思います。金融機関の話も出ましたが、地方の金融機関はどうしても新しい事業に対して消極的です。東京都が、『東京グリーンボンド』という環境に特化した債券を発行しましたが、そうして環境と金融をつなげるものが、もっと出るといいと思います」
吉高氏「大いに意義のあるディスカッションだったと感じています。みなさんの将来に役立つ内容が、ひとつでもふたつでもあったらいいと願っています。また、人と人との関係を作るのが、サロンの趣旨のひとつです。ここで話して終わりではなく、それぞれのご縁を大切につないでいっていただき、一緒にわくわくする未来を作っていきましょう」
終了後には懇親会が開かれ、参加者はよりリラックスした雰囲気の中で、互いの思いを語り合っていました。こうして胸襟を開いた交流もまた、本サロンの魅力といえるでしょう。
今回ご参加いただいた会員企業のみなさまは以下の通りです。
エーシーシステムサービス株式会社
クラブツーリズム株式会社
シャープ株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社東京国際フォーラム
東日本電信電話株式会社
前田建設工業株式会社
三菱地所株式会社
三菱電機株式会社
株式会社Unleash
株式会社環境ビジネスエージェンシー
月光荘
自然電力株式会社
西武信用金庫
大日本塗料株式会社
農林水産省
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
読売新聞
関連リンク
CSV経営サロン
2011年からサロン形式でビジネスに関する様々なプログラムを提供。発足当初から小林光氏に座長を、2017年からは吉高まり氏に副座長をお願いし現在に至っています。
2015年度からは「CSV経営サロン」と題し、さまざまな分野からCSV経営に関する最新トレンドや取り組みを学び、 コミュニケーションの創出とネットワーク構築を促す場として取り組んでいます。
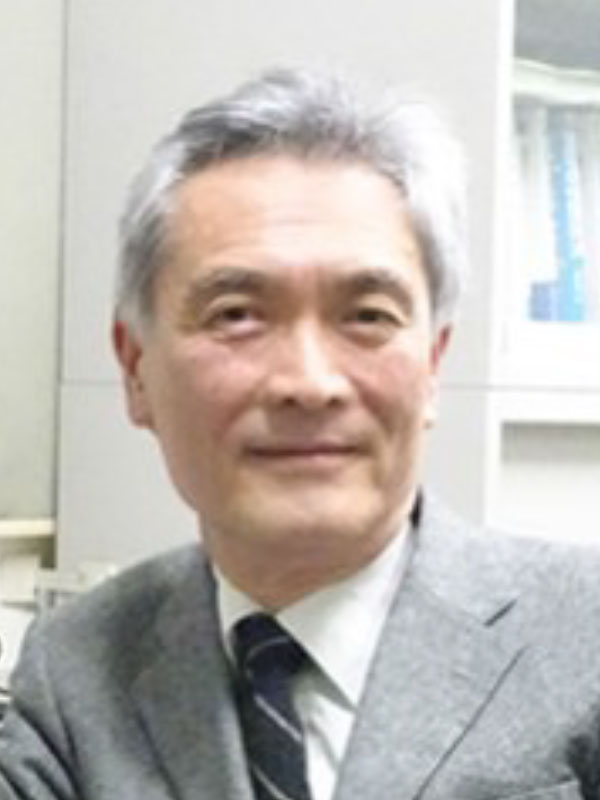
座長:小林光 氏
東京大学先端科学技術研究センター研究顧問 /
教養学部客員教授
慶應義塾大学経済学部卒(1973年)、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士、博士(2010・2013年、共に工学)。
1973年環境省(当時環境庁)入省。京都議定書交渉の担当課長、環境管理局長、地球環境局長、官房長、総合環境政策局長、2009年から2011年まで次官を務め退官。
慶應大学教授、米国イリノイ州にて派遣教授、2016年から現在まで東京大学客員教授。その他日本経済研究センター特任研究員、国立水俣病研究センター客員研究員、地方の環境審議会委員や脱炭素対策検討の委員等を歴任。
再生可能エネルギーを主要なエネルギー源とする資源循環型の社会を構築するために必要な価値観の転換、諸制度の整備などに取り組む。

副座長:吉高まり 氏
一般社団法人バーチュデザイン代表理事 /
東京大学客員教授/
慶慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
明治大学法学部卒、米国ミシガン大学環境サステナビリティ大学院科学修士、慶應義塾大学大学院政策・メディア科博士(学術)。
IT企業、米国投資銀行等での勤務を経て2000年より現三菱UFJモルガン・スタンレー証券において気候変動関連の資金枠組みづくり、カーボンクレジット組成などに関与。政府、地方自治体、金融機関、事業会社などに向けて気候変動、GX、サステナブルファイナンスの領域について講演、アドバイスなどを提供し、新たにサステナビリティ経済の推進の実装を図る。
おすすめ情報
イベント
注目のワード
人気記事MORE
- 1
 【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~
【丸の内プラチナ大学】2025年度開講のご案内~第10期生募集中!~ - 2
 【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】
【大丸有シゼンノコパン】色彩豊かな冬の鳥を「観る(みる)」 ~極寒の今こそ絶好の"鳥"日和!~【まちの生きもの】 - 3
 大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬
大丸有でつながる・ネイチャープログラム大丸有シゼンノコパン 冬 - 4
 丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト
丸の内プラチナ大学2025 逆参勤交代コース特別講座 飛騨ナイト - 5
 【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】
【大丸有シゼンノコパン】都心の緑地に春の目覚めを「覗る(みる)」~生きものとの共生のヒントを探して~【まちの生きもの/親子・初心者の大人向け】 - 6
 3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~
3×3Lab Future個人会員~2025年度(新規・継続会員)募集のお知らせ~ - 7
 【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】
【大丸有シゼンノコパン】ビルや樹々の隙間に星空を「望る(みる)」 ~「すばる」や「月」はどこにある?~【まちの星座】 - 8
 【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~
【レポート】共創がもたらす新たな価値創造 〜リビングラボが描く未来の地域経営~ - 9
 【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方
【レポート】共感が未来を動かす 〜 クリエイティブが地域に灯す、新しい価値のつくり方 - 10
 【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造
【レポート】関係資本の力を最大化する コミュニティデザインと持続的価値創造





